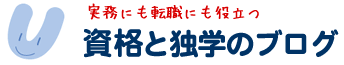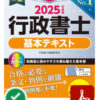宅建士の試験で高得点を得た勉強時間と勉強法
公開日:
:
宅建
この度、宅建士の試験を受け、大手5社の解答速報で自己採点したところ、45問中39問正解という高得点を得ることができました。
まだ合格発表前ですが、試験で30分くらい時間が余ったのでマークミスはないかも確認もできております。
宅建のテキストは無料テキストを使用
宅建のテキストは無料のものを使いました。
レトスの「宅建の無料テキスト」です。
このテキストのよいところは、テキストを読んで理解した後に、すぐにその内容に関連した過去問を解けるところです。
しかも過去問の量もバリエーションも豊富なので、基礎がしっかり身につきます。
また、絵や図を使って分かりやすく説明されていて、要所では分かりやすい動画も差し込んであります。
宅建の勉強の最初の4ヶ月は、この無料テキストの読み込みとその下に載っている過去問を繰り返しました。
欠点としては、改正点が反映されるのが遅かったり、正答番号が違う箇所が数か所あり、この辺は解説を読んで理解したり、ネットで調べる必要があったことです。
しかし、自分で調べたものは、記憶に残りやすいです。
改正点は予想問題集で拾えるので不自由はしませんでした。
次にネット上の無料過去問に挑戦
過去問はネット上の無料過去問(15回分載っています)を利用しました。
こちらもレトスの「宅建過去問の解説集」です。
2011年から2017年までは、レトスの無料テキストを勉強しただけで、スムーズに解けました。
この7年間の平均正答率は83%で、どの回も79%以上の正答率でした。
※過去問を勉強するときは、正解枝だけでなく、他の選択枝も勉強しましょう。
なぜその選択枝が正解なのか、なぜ他の選択枝が不正解なのか理由が分かるようにしておきましょう。
ところが、2018年の過去問に着手したところ、民法で間違えた個所が多くなり、無料テキストと無料過去問だけでは余裕を持った合格は難しいことが分かりました。
(それでも合格ボーダーあたりには達していました)
オリジナル問題で応用力をつける
そこで一旦過去問を中止し、LECの「2024年版 出る順宅建士 一問一答○×1000肢問題集」をやってみました。
この問題集はオリジナル問題で応用力をつけるのに適しています。
また、通勤時間や休憩時間等コマ切れ時間に解けるのもこの問題集の長所です。
出る順宅建士1問1答集の初回の正答率は85%。
悪くはない正答率ですが、もう少し踏み込みたいところ。
そして、間違えたところを解説を読んで理解したり、解説だけでは理解できない部分はネットで調べました。
そのうえで再度解きなおし、95%以上の正答率にしました。
再度、宅建の無料過去問に戻り、2018年以降の問題を解くと平均正答率が78%に上がりました。
この時点で、勉強期間は5ヶ月程度で勉強時間に換算して250時間です。
とはいえ、71%の正答率の回が3回あったので、この時点ではまだ合格ボーダーライン。
安心はできません。
レトスの「宅建過去問の解説集」の解説をしっかり読み込み、3回以上繰り返し解きました。
そして宅建の年度別過去問はどの回も90%以上の正答率に持っていきました。
分野別過去問は関連した1問1答付のものを使用
宅建の無料過去問とLECの1問1答集を制覇した後に行ったのが、「この1冊で合格! 水野健の宅建士 神問題集」です。
この分野別過去問集は、過去問だけでなく、その過去問に関連した1問1答がついており、応用力を上げるのに適しています。
過去問は年度別過去問を制覇していたので、ほとんど正解しました。
そしてその過去問に関連した1問1答の正答率は85%だったので、間違えたところを繰り返し解いて復習しました。
この時点で、宅建の勉強時間は300時間となりました。
宅建合格に必要な勉強時間は300時間と言われますが、まさしくその通りで300時間正しい方法で勉強すると合格ラインを越えます。
仕上げは予想問題集2冊
6月に入ると、大手予備校から宅建の予想問題集が発売されます。
私はLECの予想問題集と日建学院の予想問題集を行いました。
LECの予想問題は全部で4回分あり、4回分解いて初回の平均が80%超えていました。
1番低い回(難易度が高い回)でも正答率76%だったので、十分合格点を超えている状態でした。

LECの宅建予想問題集
※今後宅建を受験される方は新しい年度のものをお使い下さい。
なお、LECの予想問題集のアンケートに答えると、前年度の宅建士模試と法改正資料がもらえるので、アンケートには答えておきましょう。
この時点で宅建の勉強時間は400時間。
400時間勉強すると少し余裕のある合格を狙えると感じました。
その次に行ったのが、日建学院の予想問題集です。
3回分解いて平均が80%を超えていました。
新傾向・未出題論点てんこ盛りの第3回でさえ、76%の正答率でした。
この日建学院の予想問題集第3回は、本試験でも類似問題が何問か出題されており、そのうち1問は難問でした。
さらにこの日建学院の予想問題集に付属の重要数字チェックドリルをマスターしていれば解ける問題も出題されていました。
日建学院の「これで合格!宅建士直線予想模試」は、今年に限らず難問を当てたという実績があり、宅建の予想問題としておすすめです。

日建学院の宅建予想問題集
※今後宅建を受験される方は新しい年度のものをお使い下さい。
この時点で宅建の勉強時間は475時間。
宅建は500時間勉強すると余裕を持った合格を狙えるというのが私の実感です。
300時間でも合格ラインを超えることができますが、余裕を見るなら500時間といったところです。
宅建の勉強期間としては6~10ヶ月くらいですが、残業の多い仕事をしている方は1年くらいかけてもよいかと思います。
直前チェックもお忘れなく
宅建の試験日直前は、自分が間違えやすい問題や引っかかりやすい問題の復習をしていました。
そして自分が忘れやすい論点のメモも読み込みました。
この努力が実り、直前でチェックした知識を使って解く問題が出題され、確実に得点することができました。
また、試験会場入り口で配られていた日建学院の「宅建士への道」に重要ポイントがあり、試験直前にチェックしたため、スムーズに解くことができました。
宅建士に限らず、どの試験にも言えることですが、最後の最後まで気を抜かないことが合格の秘訣です。
結局、宅建士受験までの勉強期間は独学で約1年、勉強時間は600時間近くとなりました。
残業ありで働きながら独学で勉強するのであれば、勉強期間半年で合格ラインを超えることができ、勉強期間8ヶ月で少し余裕のある合格、1年でかなり余裕のある合格を狙えるのが、宅建の試験を受けてみての私の実感です。
関連記事
-

-
宅建の民法は難しい?勉強法は?捨てる選択はアリ?
私は、宅建の勉強をしていて民法が特別難しいとは思いませんでした。 というのもテキストはレトスの
-

-
宅地建物取引士証の交付手続きから入手まで
宅地建物取引士の登録手続きから約1ヶ月(30日)で登録通知のハガキが届きました。 会社から帰宅する
-

-
宅建の登録実務講習に行ってきました!
先日、宅建の登録実務講習を受けてきました。 試験に合格して宅地建物取引士の登録を受けるには、2
-

-
宅建試験を受けた後は登録実務講習の早割申し込みを検討
宅建試験を受けて合格証書をもらったら、即宅建士になれるわけではありません。 宅建士の登録には2
-

-
宅建の登録講習に行ってきました。
6月1日土曜日、宅建の登録講習に行ってきました。 この登録講習を受けると本試験の5問が免除され
-

-
宅建の試験を受けたところ86%の正答率でした
先日、宅地建物取引士(宅建)の試験を受けてきました。 帰って大手5社の解答速報で自己採点してみ
-

-
宅建士の登録申請手続きに行ってきました
1月下旬に宅建士の登録手続きに行ってきました。 受験地が大阪なので、大阪府咲洲庁舎での登録申請とな